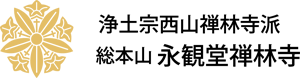愛知県一宮市 コハクチョウ 撮影: 超空正道
夢
先日、法務のため北に向けて走行しておりましたら、突然霧雨になりました。しばらくして西に進路を変えると、前方に、虹の左端の立ち上がる部分が、直ぐ目の前に迫ってくるような感じに見えて、実に美しい光景でした。私のような老齢になりましても、突然邂逅する虹の出現には感動を覚えてしまいます。この虹といえば、ミュージカル映画『オズの魔法使い』で、ヒロインのドロシーが歌う『虹の彼方に』を連想するのは私だけではないでしょう。こんな歌詞になっています。
どこか虹の彼方に
空の向こうに
夢の国があるって
どこか子守唄で聞いたことがあるの
どこか虹の彼方に
青空が広がっていて
心に描く大きな夢が
本当に叶うところがあるの
いつか星に願いをかけるわ
そして雲よりずっと上の
空で目を覚ますの
悩みもレモンドロップのように
溶けてなくなる
えんとつより遥か上
そんなところに私は行きたい
どこか虹の彼方に
青い鳥たちが飛んでいる
鳥たちが虹の向こうに
飛んでいけるなら
きっと私だって飛べるはずだわ
……いかがでしょうか。確かに、虹の彼方に行けば、夢を叶えてくれそうな世界があるような心持ちにさせてくれます。この映画が出来たのは、ちょうど第二次世界大戦が始まった1939年で、世の中全体が先の見えない不安に包まれていた時代でした。昨今も、長いコロナ禍、そしてロシアのウクライナ侵攻といった暗い世相であるところから、この曲に共感を覚える方も少なくないのではないでしょうか。
ところで、話はいきなり『般若心経』に飛びますが、夢について考察してまいりましょう。お経の中程に「菩提薩埵 依般若波羅蜜多故 心無罣礙 無罣礙故 無有恐怖 遠離一切顛倒夢想 究竟涅槃」とあり、「観音菩薩は、真実の智慧を得ているがゆえに、心にこだわりが無く、こだわりが無いから恐れるものも無い。一切の顛倒した考えや夢想することから離れて、悟りの境地に至っている」と言う意味が書かれています。つまり、夢を見るという行為は、迷い惑う心があるからして、無明なるがゆえにそうさせるのであって、真実を見極めることが出来る冷静な目を持っていれば、そのような儚いものに希望を託すようなことはないということです。この迷妄に関して、昭和の名僧、内山興正老師が生前されていた面白い話を紹介いたしましょう。
ある寒い夜中に、カラコロ歩いていると、道路に見るからに分厚い中身が入っていそうな財布が落ちている。辺りをキョロキョロして誰も居ないのを確かめ手を伸ばすも、凍てついていて取るに取れない。ならば、「グッドアイデア!、小便かけて氷を融かしてやろう」というんで、「いざ」と思うがなかなか出ない。いよいよ思い切って「ジャー」としたら目が覚め、そして翌朝、濡れた布団を干す羽目になってしまったと言うわけです。
そこで内山老師は、「思いは幻影、行為は現実、結果は化けて出る」という公式を明かしておられます。すなわち、われわれは時として夢ような、現実不可能なことに希望を抱いて、無駄な行為をするが、当然結果は意に反して思いも寄らない、悲惨な結果が待っているものだというのです。
確かに、われわれの無明の曇った眼で今見ている現象は、幻影に過ぎないのに、本物と思い込んで徒労を重ねて、「何をやっても上手くいかない。自分は運に見放されている」と思っている人が実に多いものです。先の『オズの魔法使い』のドロシーも、どういう事情か分かりませんが、叔母夫婦に養われています。周りの人間は、自分にかまってくれないと感じています。さらに、意地悪なおばさんが、自分にとって一番大切な愛犬のトトを取り上げようとします。そこで歌われるのが『虹の彼方に』です。そして、夢を叶えてくれるというオズの魔法使いに、苦労して会いに行くのですが、実はそれは詐欺師だったのです。結局夢は叶えられずに元の家に戻ってくるのですが、本当の幸せは身近にあったことに気づかされるのです。
仏教でいう「成るべくして成る」「蒔かぬ種は生えない」といった因縁生起の教えからは、夢が入り込む余地はあまりありません。しかし、それではあまりに夢がなさ過ぎます。真実を見極めることのできる、正しい見識を得たいという智慧の獲得と、浄土極楽往生への夢は、希求し続けたいものです。
(潮音寺 鬼頭研祥)