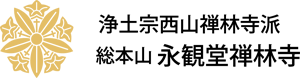豊臣秀吉像
豊臣秀長像
永観堂の所蔵する寺宝をお届けします。展示会などでは間近に見ることの少ない寺宝をお楽しみください。
永観堂とつながりの深い豊臣家の秀吉像、秀長像をお届けします。なお、表示画像は見やすくするため画像処理を施しています。実際の色合いや明瞭さと異なることがあります。
豊臣秀吉像、豊臣秀長像
解説
豊臣秀吉像
白装束を着し三重の上畳に威儀を正して坐る秀吉像。蟇股を設けた長押からは幡幕を降ろし青畳には暈繝縁を用いる点は、像主の神格化が窺える。右手には笏を持ち、左側には太刀が置かれる。背後には大振りの桐樹を水墨で描く。禅林寺における秀吉像については当寺所蔵当麻曼荼羅の慶長十二年裏書に、豊臣秀頼の指示により四天王寺曼荼羅堂を移築した本堂(阿弥陀堂)の中央にみかえり本尊を安置し右檀に大曼荼羅、左檀に豊国神像を掛けたことを伝える記載がある。本図はこの豊国神像にあたるものと考えられる。秀吉は禅林寺にとって大壇越の一人と数えられ、当寺には天正十三年(1585)と十七年の秀吉朱印状が伝えられている。
111.0cm×52.8cm
安土桃山時代
豊臣秀長像
寺伝では、秀吉像とともに太閤像として伝来してきたものであるが、近年、この他の秀長像との像様の類似から、これが秀吉の弟である大和大納言豊臣秀長(?~1591)の肖像であることが指摘された。近世初期の禅林寺にとって豊臣家は重要な位置を占め、秀吉は当時の大壇越の一人と数えられその画像が本堂に豊国大明神として祭られた。しかし、秀長と当寺との具体的な関連は未詳であり、本図が制作され当寺で祀られた経緯についても明らかでない。
101.7cm×42.6cm
江戸時代前期